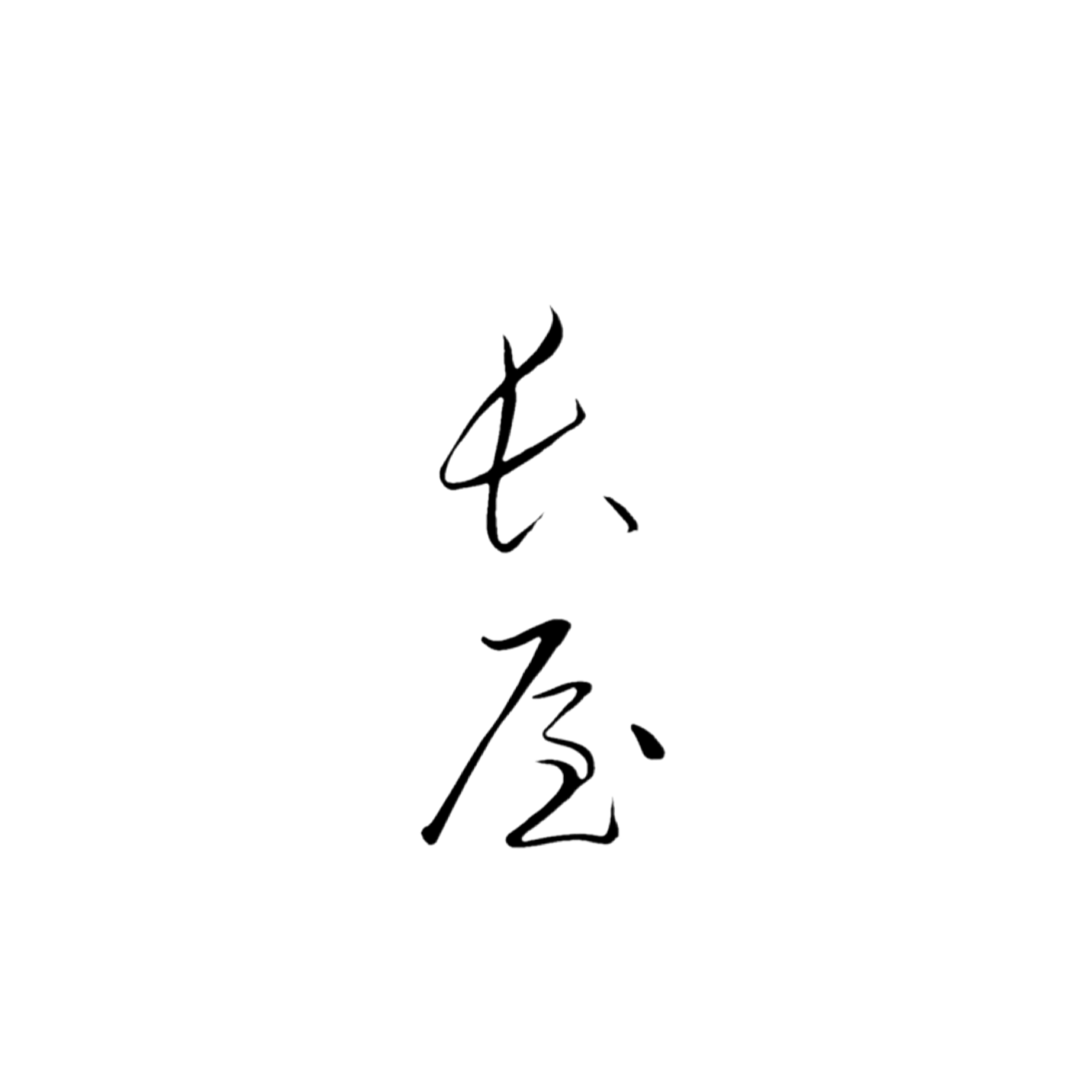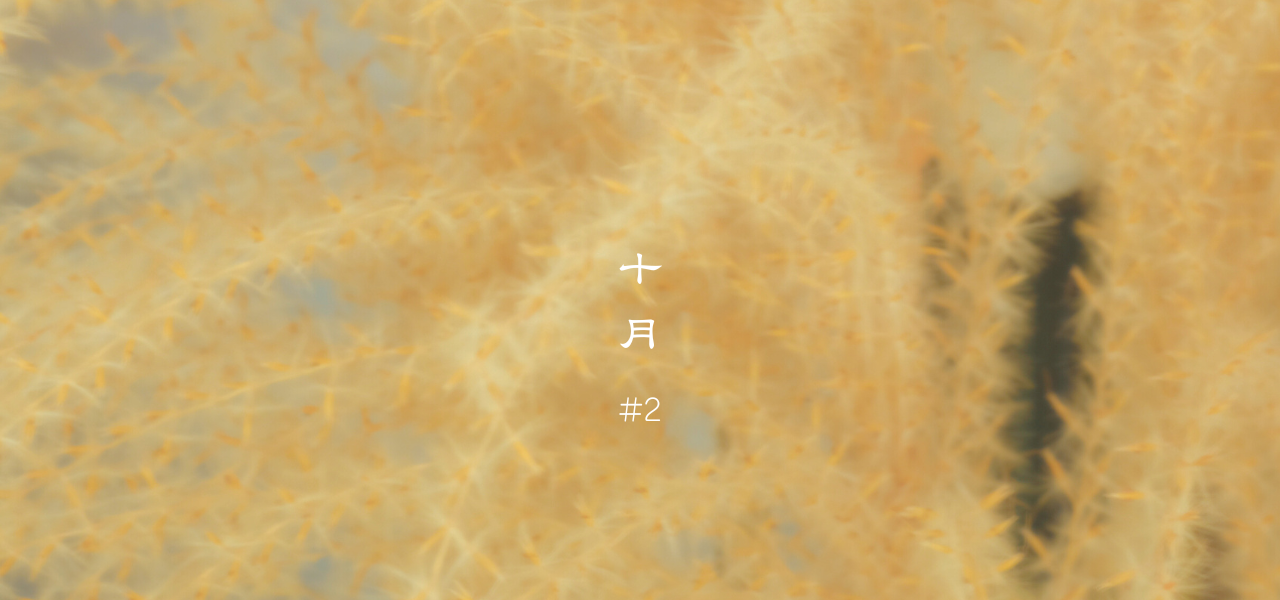記事: 冷えは“滞り”のサイン 〜親子でととのえる、あたたかい巡り〜
冷えは“滞り”のサイン 〜親子でととのえる、あたたかい巡り〜

朝の空気がきりっとして、息が白く見える頃になりました。
秋が深まり、冬の足音が聞こえてくる11月。
気づけば、足元からじんわりと冷えが忍び寄ってきます。
冷えは、ただ「寒い」という感覚ではなく、体の内側で“巡り”が滞っているサインでもあります。
放っておくと、肩こりや生理痛、胃腸の不調、そして気持ちの落ち込みにも。
この時期に、しっかりと養生することで冬の体が変わってきます。

ー冷えるとは?
東洋医学では、冷えは「気・血・水」の巡りが滞った状態とされます。
体を温めるエネルギーを生み出す「脾(消化吸収)」や、「腎(生命エネルギー)」が弱ると、
血の流れや代謝が低下し、内側から冷えが広がります。
つまり、冷えとは“エネルギーの流れが止まりかけている”という体の声。
そのサインを見逃さず、少しずつ巡りを取り戻していくことが、これからの季節を快適に過ごす鍵になります。
ー子どもと大人の“冷え方”の違い
子どもと大人では、冷えの出方も少し違います。
子どもは「陽気(エネルギー)」が旺盛で基本的には温かい体ですが、
体温調整の機能がまだ未熟なため、朝晩の冷えに対応しづらく、
手足の冷え、鼻水、咳、疲れやすさ、眠りの浅さなどとして現れやすいです。
大人は、エネルギーを消耗しやすい世代。
忙しさやストレス、冷たい飲み物の習慣などで気や血の巡りが滞り、
下半身の冷え、生理痛、胃腸の不調、肩こり、気分の落ち込みとして現れることも。
だからこそ、
子どもには「守るあたため」に
大人には「巡らせるあたため」に
一緒にできる、秋の養生法が必要なのです。

ー秋の親子養生のおすすめ
・朝、白湯や温かい汁物で内臓をやさしく起こす。
・お腹・腰・足首を冷やさない。腹巻きや靴下を身につける。
・軽いストレッチや散歩で気の巡りをよくする。
・湯船にゆっくり浸かり、深呼吸で一日の疲れを流す。
特別なことをしなくても、こうした日常の“あたための習慣”を重ねるだけで、
体は少しずつ柔らかく、心まであたたかくなっていきます。
ー台所でできる秋の養生レシピ
・焼きねぎとれんこんの味噌汁
香ばしく焼いたねぎと、すりおろしたれんこんを加えた味噌汁。
喉を潤しながら、体を芯から温めてくれる一杯です。
ねぎの香りは気の巡りをよくし、れんこんのとろみがやさしく胃を包みます。
・塩麹の雑穀粥
冷えで疲れた胃腸をいたわるには、やわらかく炊いた雑穀粥に塩麹をひとさじ。
体を温めながら、消化の力を整えてくれます。
朝のあたたかい粥は、冷えたお腹を内側からほぐす最高の一杯。
・黒甘酒と黒ごま・くるみの和えもの
黒甘酒に黒ごまとくるみを合わせた、濃厚で滋養たっぷりの小さなデザート。
「黒」は腎を補う色。冷えや疲れを癒し、生命力を深めてくれます。
おやつや食後のひとくちにもおすすめ。
冷えは、体の「内なる流れ」が止まりかけているサイン。
そこに“あたたかさ”を少し足してあげるだけで、体はまた動き出します。
今日の白湯、今日の湯船、今日のごはん。
そのひとつひとつを親子でコツコツと
冬を迎える準備をしていきましょう。
養生家 鈴