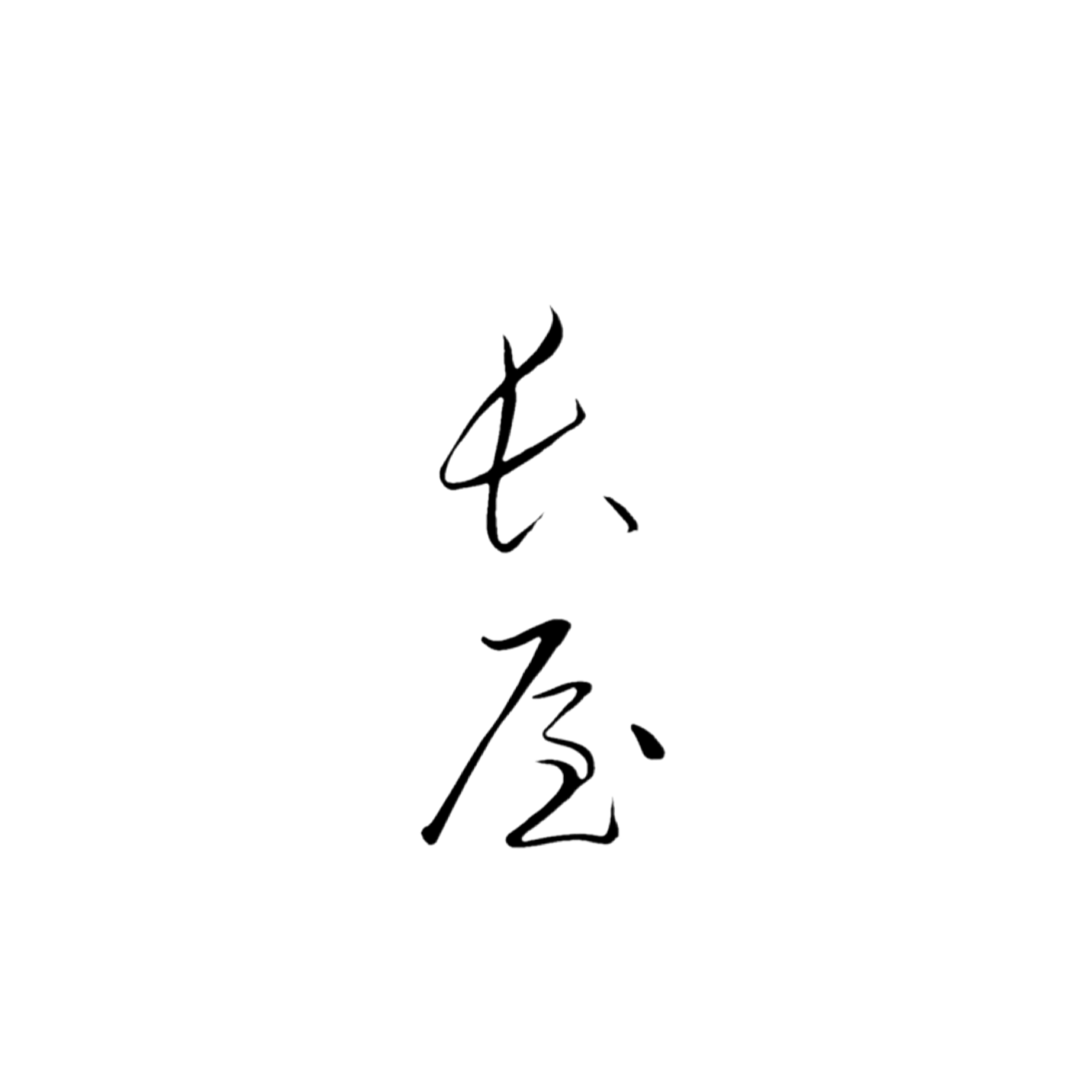野菜の味噌汁とごはんで、お腹をととのえる 〜台所は、わたしの薬箱〜
 子どもが学校へ行き、ようやく家の中が静かになった朝。
子どもが学校へ行き、ようやく家の中が静かになった朝。
台所に立ち、ふと「疲れが抜けないな」と感じるときがあります。
頭ではやることをわかっているのに、体も心もついてこない──
そんなとき、私はあたたかい味噌汁をゆっくりいただくことにしています。
包丁のを入れる音、野菜の香り、お出汁の湯気。
それだけで、すこしずつ心が落ち着いて、なんだか「大丈夫な気がする」のです。
腸は“第二の脳”、心の元気と深くつながっている
東洋医学でも、腸を含む消化器系は「脾(ひ)」とよばれ、私たちの気や血、水のめぐりを整える中心とされています。
腸が疲れていると、気が巡らず、気分まで重たくなるのはそのためです。
最近の研究では、「腸は第二の脳」ともいわれるようになりました。
実際に、幸せホルモンと呼ばれるセロトニンのほとんどが腸でつくられています。
つまり、腸が元気なら、心も明るくなる。
台所でととのえるのは、からだだけでなく心のバランスでもあるんですね。
 味噌汁とごはんは、“しあわせの基本セット”
味噌汁とごはんは、“しあわせの基本セット”
腸と心を元気にしたいとき、まずは「朝ごはんに味噌汁とごはん」。
とてもシンプルですが、これがじつはいちばんの薬になります。
ポイントは、味噌汁の具材を旬のものをしっかり入れること。
ごぼう、にんじん、キャベツ、玉ねぎ、小松菜、きのこ類──
ちょっと旬のものがわからない。そんな時は冷蔵庫にあるもので十分です。
今の季節は、新玉ねぎや春キャベツが甘くておすすめ。
発酵食品である味噌は、腸の善玉菌のエサにもなります。
たっぷりの野菜とあわせると、腸の動きがスムーズになって気持ちまで前向きに。
長屋の麹調味料もうまく組み合わせるととてもいいですね。
【おすすめ具材の組み合わせ】
・新玉ねぎ+キャベツ+油揚げ
・ごぼう+にんじん+しめじ+ねぎ
・小松菜+豆腐+舞茸+味噌+すりごま
【長屋麹のおすすめの使い方】
朝起きた自分を感じて決めれるちょい足しです。
・やる気がでない時は醤油麹を
・お腹がゆるいときは塩麹を
・緊張がある時は甘酒(白)を
そこに炊きたてのごはんがあれば、それだけで「ととのうごはん」の完成です。
 忙しい日こそ、台所を自分の“養生の場所”に
忙しい日こそ、台所を自分の“養生の場所”に
家族の食事を優先して、自分の食べるものはおろそかに──
そんな日が続くと、体も心も“空っぽ”になってしまいます。
でも、朝10分だけ、自分のために味噌汁を作る時間があれば大丈夫。
それは、食事という形の「セルフケア」になります。
ごはんと味噌汁の香りは、どこか懐かしくて、心をゆるめてくれる。
台所は、道具も材料もそろっている“わたしの薬箱”です。
おわりに:台所で、自分にやさしくすることから
味噌汁とごはん。
一見、なんてことのない組み合わせですが、そこには「養生の知恵」が詰まっています。
何かを“足す”よりも、まずは整える。
慌ただしい毎日の中で、自分の心と体の声を聞きとるのは難しいけれど、 「朝、味噌汁を作る」ことが、そのきっかけになることもあります。
今日の味噌汁が、あなたの心をやさしく包みますように。
そしてまた、明日も、台所から元気をつくっていけますように。